第71回 マツタケ人工栽培究極の会 令和7年7月19日の記録
祇園祭り山鉾巡行も、17日雨天の中 無事終わり、
一昨日とは打って変わって、本日19日は梅雨明け土用の陽光です。


僕(昆虫少年)の中の歳時記では、
ヤマトタマムシが、エノキの樹冠を飛ぶ季節です。
参加者は、
Dr.大島、近藤、野村、濱崎、藤田博美、藤田利幸、吉原 の全7名でした。
【補助金で】栽培中のマイタケの
覆土が雨で剥がれて直射日光が当たると、
菌がダメになるかもしれない。(藤田林業)
という事で、栽培地を見に行って来ました。

覆土の一部が流出して木漏れ日が射していますが、
杉木立と檜に囲まれた適地で、
superviserの吉原さんに依ると、
8月は当会が休会ですが、直射日光は、
寒冷紗を掛けずとも、9月迄は大丈夫だそうです。
「光合成細菌」を撒いて、PH調整するのはどうでしょう?
という提案が、藤田利幸さんからありました。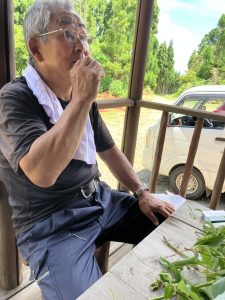
「光合成細菌」は、光と水があれば、何処でも殖えて、寄生ではなく
「独立栄養生物」として、水素や組成の良いアミノ酸を生成し、
「窒素固定」するという意味で、農業にとって素晴らしい菌類です。
全ての生物は、一定 利他的でないと存続出来ません。
光合成細菌(通称:赤菌)のPHは6〜8で、施業地に撒く事で、
PH3.5ぐらい酸性に傾いた松林を、マツタケに適した
PH4.5ぐらいに戻す事を目標にしています。
大島先生は、光合成細菌の論文を発表した事もあるそうです。
僕は、久しぶりに小林達治先生の名を聞きました。
小林達治先生はDr.関谷次郎(京大名誉教授/当会会員)とも縁の深い先生です。
小林正美博士は小林達治先生の息子さんで、
筑波大学で藻類(光合成細菌)の研究をされています。
そもそも、22億年前に【藍藻類(アオミドロ)】が地球に登場して、
地球の大気の20%を酸素にしたのです。
鉄鉱石を作ったのも、光合成細菌のシアノバクテリア(藍藻類)です。
昼食の後は、植物の同定会をしました。
松林の、植物(木本/もくほん)は、約100種類だそうです。
日本列島では、木本は4500種です。

20〜30種類、聚めました。

木本 アセビ、コナラ、ソヨゴ、ヒサカキ、コバノミツバツツジ、リョウブ、シキミ、クロモジ、モチツツジ、サルトリイバラ、アクシバ、スノキ、ナナメノキ、アスナロ(アテ)、ユズリハ、ウリハダカエデ、コウヤマキ、、、
草本 マムシグサ、ウラジロ、クジャクシダ、タケニグサ、イヌホウズキ、クサイチゴ、
大島先生は、例会以外にも、土壌改良や、柴刈りに来られるそうです。
皆さま、お疲れ様でした。
記 野村龍司
【8月31日の活動報告】
1)舞茸栽培埋設地にドーム型寒冷紗を設置しました。
2)参加者・・・藤田(利)、吉原
3)設置状況 ①玉木上部の流失被覆土の埋め戻し。 ②鉄線支柱をドーム型に設置。 ③寒冷紗遮光率80%を設置。 ④ドーム裾を材木で押さえ。 ⑤所要時間 1時間で完了。
4)今夏の状況から発生時期が10月15日前後にズレこむか?